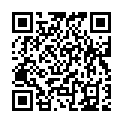所属している「八王子南多摩建築組合」(八王子市本町)で実施された講習見学会で、東京ガス・新宿ショールームの見学に社長が参加。
所属している「八王子南多摩建築組合」(八王子市本町)で実施された講習見学会で、東京ガス・新宿ショールームの見学に社長が参加。
古今東西、新旧のガス施設のある中で、興味を持ったレトロな品物の何点かを写真に撮ってきて下さったのでUPします。
これは、「明治10年の第1回内国勧業博覧会で出典されたガス灯」で、
現在のイルミネーション(電飾)にあたるものらしいです。
 東京で最初にガス灯がついたのは、明治7年に「銀座れんが街」で。
東京で最初にガス灯がついたのは、明治7年に「銀座れんが街」で。
明治11年には、「鹿鳴館」にガス灯がともり大評判となり、以降、
街灯や皇族邸などへガスは広がって行ったそうです。
明治13年に「東京電灯」が設立され、ガス灯は人気凋落。
当時のガス灯は、石炭を蒸し焼きにして作った裸火だったので、ロウソクの1.5倍の
明るさしかなかった上に、電気と比べてガス代がかなり高かった為だそうです。
それゆえがどうか、東京府は明治18年にはガス事業を民間に払い下げたそうで、
これが東京ガスの誕生となった・・・ということらしいです。
そんな昔から、ガスと電気はライバル同士だったのですね。
 昭和の作だと思いますが、
昭和の作だと思いますが、
カニ形をした「ガスストーブ」の写真がありました。
真ん中の蜘蛛の巣状に広がる白い線?の所に、
ほのかに赤い炎が燃えていたのでしょうか。
こんなストーブがあったら、欲しいなと思ってしまった次第でした。
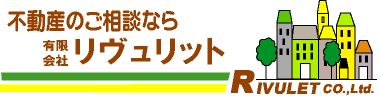



 「西日本豪雨」で
「西日本豪雨」で